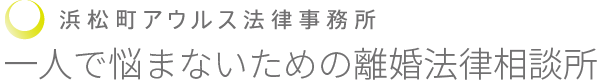財産分与の審判に対する不服申立についての最高裁判例
弁護士 幡野真弥
最高裁令和 3年10月28日決定をご紹介します。
■事案の概要
離婚をしたXとYが、それぞれ、財産分与の審判を申し立てた事案です。
経緯は次のとおりです。
(1) XとYは、平成29年8月9日に離婚をした。
(2) Yは、令和元年8月7日、Xに対し、財産の分与に関する処分の調停の申立てをした。
(3) 上記の調停事件は、令和元年11月、不成立により終了したため、(2)の申立ての時点で、財産分与の審判の申立て(第1事件の申立て)があったものとみなされた(家事事件手続法272条4項)。
(4) 令和2年3月、Xは、Yに対し、財産分与の審判を申し立てた(第2事件)。
(5) 原々審(家庭裁判所)は、第1事件及び第2事件の各申立てをいずれも却下する審判をした。
(6) Xは、上記審判に対する即時抗告をした。抗告審(高等裁判所)は、第1事件に係る即時抗告を却下した。
■最高裁の判断
家事事件手続法156条5号は,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,夫又は妻であった者が即時抗告をすることができるとしている。これは,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,当該審判の内容等の具体的な事情のいかんにかかわらず,夫又は妻であった者はいずれも当然に抗告の利益を有するものとして,これらの者に即時抗告権を付与したものであると解される。
したがって,財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である当該申立ての相手方は,即時抗告をすることができるものと解するのが相当である。
以上と異なる見解に立って,本件即時抗告のうち第1事件に係る部分を却下した原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原決定中,主文第1項は破棄を免れない。そして,更に審理を尽くさせるため,同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
■説明
たとえば、民事裁判で、原告が被告に対して損害賠償を求めて訴訟を提起した場合、判決で、被告が完全に勝訴した(原告の損害賠償請求が1円も認められなかった)とき、負けた原告は控訴することができますが、完全に勝った被告は控訴することができません。勝った以上、控訴して有利な判決を求める利益がないためです。
家事事件でも同じように考えると、YがXに財産分与を求めた審判事件で、財産分与が1円も認められず、Xが勝ったのであれば、Xに不服を申し立てる利益がないことになります。
本件では、XもYに対して財産分与の審判を求めている(第2事件)ことから推測できることですが、財産分与の審理をしてみたところ、Xの財産より、Yの財産の方が多く、本来はYがXに財産分与する関係になったものと思われます。しかし、財産分与は、離婚成立から2年以内に求めないといけないところ、第2事件の申し立ては、離婚から2年が経過した後になされています。そのためXからの第2事件の審判申立は、裁判所に却下されています。そこで、Xとしては、第1事件について不服を申し立てることとしたものと推測されます。
抗告審では、民事裁判の場合と同じように、「第1事件の申立てを却下する審判は,第1事件においてXが受けられる最も有利な内容であり,Xは抗告の利益を有するとはいえないから,即時抗告をすることができず,本件即時抗告のうち上記部分は不適法である。」と判断しました。
しかし、最高裁は、上記のとおり「家事事件手続法156条5号は,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,夫又は妻であった者が即時抗告をすることができるとしている。これは,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,当該審判の内容等の具体的な事情のいかんにかかわらず,夫又は妻であった者はいずれも当然に抗告の利益を有するものとして,これらの者に即時抗告権を付与したものであると解される。」と判断し、Xの抗告の利益を肯定しました。
この後、第1事件は広島高裁に差し戻され、再度、広島高裁の判断を受けることになりますが、「財産分与の審理をしてみたところ、Xの財産より、Yの財産の方が多く、本来はYがXに財産分与する関係にあった」とすると、広島高裁で、「YはXに対し、財産分与を支払え」と命じることができるのでしょうか。第1事件は、「Yが財産分与を求めた事件」です。この論点は「財産分与の義務者からの財産分与の申立は可能か」という観点から議論される事が多いです。仮に、財産分与義務者からの申立は認められないとすると、広島高裁でも、結局はXに対しは財産分与を受ける判断を受けることができなくなってしまいます。財産分与義務者からの財産分与の申立について、実務や学説は分かれていますが、否定的な考えも有力でしたので、この点について広島高裁がどのような審理・判断をしたのか気になるところです。