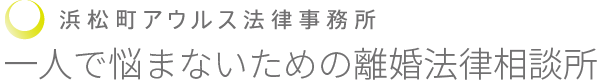有責配偶者からの離婚請求が認められなかった裁判例
弁護士 幡野真弥
離婚を認めた原判決(東京家裁令和 2年 3月31日判決)を変更し、有責配偶者からの離婚請求として離婚を認めなかった東京高裁令和 3年 1月21日判決をご紹介します。
原告と被告は、平成2年6月13日に婚姻し、両者の間には長男A(平成3年)、長女B(平成6年生)及び二女C(平成9年生)がいました。
原告は、平成29年5月6日に自宅を出て別居を開始しました。
原告と女性とは、平成30年5月の時点で、肉体関係を伴う交際を行っていました。
原審は「原告が,平成28年12月頃,原告の両親と平成29年12月に同居する計画について述べたことをきっかけに,原告の両親との今後の関係についての協議が始まり,同年4月に行われた話合いの際には,被告は,原告に対し,「異常人間」,「犯罪者」,「根本的に間違ってる」などとその人格を非難する発言をし,また,5000万円で神戸にマンションを買い,さらに5000万円慰謝料を支払うことを求めるなど,離婚や財産分与を前提とした発言をしている。」「原告として,これらの発言が自らに対する侮辱であったり,被告が離婚に伴う慰謝料や財産分与の支払を求めるものと理解することには十分な理由がある。そして,上記認定事実からすると被告が子宮腺筋症に罹患していたことや,従前の婚姻関係における原告の振る舞いに不満を持っていたことが被告による原告への発言をやむを得ないものとする理由となるとは解されないし,被告の原告に対する「異常人間」,「犯罪者」などの表現が,通常の婚姻関係の中における諍いの範疇にとどまるものとは評価できず,被告の上記の発言等は,原告として別居を決意する十分な理由となったものといえる。」と判断し、さらに有責性については「被告は,原告が有責配偶者であると主張するが,上記の被告の原告に対する侮辱的な言動の程度や,別居時に既に原告がDと肉体関係を有していたとまでは認められず,認められるのは別居から約1年後にとどまることなどからすると,原告とDとの肉体関係が,婚姻関係破綻の主たる原因であるとまでは認められず,原告は有責配偶者であるとはいえない。」判断しました。
一方で控訴審である東京高裁は「一審被告は,一審原告の両親との対応や,一審原告の両親のもとに引き取られた後の二女との対応について,不満を募らせ,極端に取り乱したことがあったが,それも特定の時期における限定的なエピソードであり,その他の一審原告と一審被告の喧嘩は,通常の夫婦喧嘩の域を出るものではなかったというべきである。」 「(一審原告は)一審被告が二女に対する不満を話し始めると,それを録音し(甲4の2),同月20日に至っては,自ら今晩で決着をつけるために話し合おうと一審被告を誘導して,これを録音している。その際の一審被告の話の内容は,ほとんどがそれまでも幾度となく行われてきた会話の繰り返しであることは,一審原告の対応から十分に推認でき,一審被告が語る内容は財産分与に及んでいるものの,多分に夢想的な部分を含むものであることは,当事者双方が互いに十分認識し合っていたものと認めることができる。一審原告の録音意図を別にしても,上記の当時において,一審原告と一審被告の婚姻関係が破綻していたということは困難である。」
と判断し、有責性については「一審原告は,本件訴えを提起した平成30年11月9日の時点においても,Dと不貞関係を継続していたというべきであるから,一審原告の離婚請求は,有責配偶者によるものといわざるを得ない。」と判断しました。
控訴審の判断のうち、破綻の程度に対する認定部分は厳格に過ぎると思いますが、裁判となった場合、ここまで厳しく評価されてしまうおそれがあるということは認識しておく必要がありそうです。