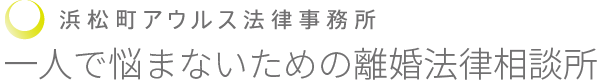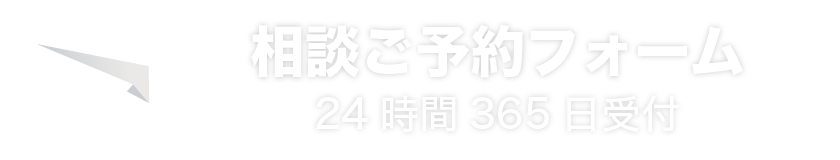離婚後共同親権の場合、監護者は何ができるのか?
弁護士 長島功
親権には子どもの身の回りの世話や教育を行う身上監護権と子どもの財産管理をする財産管理権があり、監護権というのは身上監護権のことを指します。
このように監護権は親権の一部をなすものですから、通常、親権者であれば監護権も有していることになります。ただ、協議や家庭裁判所の判断を経て、一方の親を親権者、他方の親を監護者とすることも可能で、この場合、現在の法制度の下では親権者は財産管理のみを行い、監護者は身上監護を行うということになります。
では、改正民法により離婚後共同親権とした場合で、父母の一方を監護者と定めた場合、この監護者は何ができて、親権者とはどのような関係になるのでしょうか。
この場合、監護教育に関する重要な事項(日常行為以外の行為)は、急迫の事情がなくても監護者は単独でできます(改正民法824条の3第1項)。また、監護者でない親権者は監護者の身上監護を妨害してはならない(改正民法824条の3第2項)とされています。言い方を変えれば、監護者ではない親権者も監護者の身上監護を妨げない範囲で監護教育に関する日常行為を行えますが、身上監護に関する事項について父母間で対立が生じた場合には、監護者の意見が優先されることになります。
なお、父母の一方が監護者に指定された場合であっても、共同親権の場合、親権の行使は単独で行使できる場合を除いて、原則として共同で行使する必要はあります。