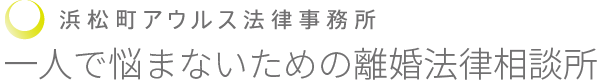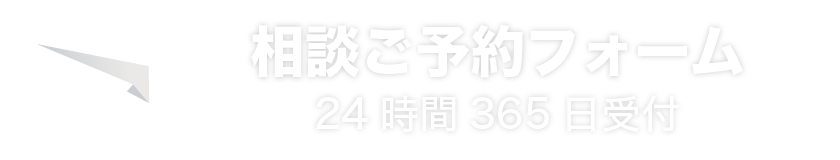共同親権は誰がどのように決めるのか
弁護士 長島功
離婚した後も父母の共同親権を可能とする民法等の一部を改正する法律が令和6年5月に成立・公布され、公布から2年以内に施行されることになっています。そこで、今後施行されるこの共同親権の内容について、順次解説をしていこうと思います。
1 選択制
まず、導入される共同親権の制度ですが、父母が離婚した後も原則として共同親権になるというものではありません。諸外国ではこうした立法がなされているところもありますが、改正民法では離婚時に共同親権とするか単独親権とするかをまず父母の協議に委ねるという制度になっています(改正民法819条1項)。
そして、父母の協議で合意が成立しない場合、または裁判離婚の場合には、家庭裁判所が共同親権とするか単独親権とするかを定めるということになっています(改正民法819条2項・5項)。
このように、共同親権の制度が導入されるといっても、原則共同親権になるという建付けではなく、あくまで選択的なものとなっています。
2 裁判所の判断基準
上記のとおり、共同親権とするか単独親権とするかは、まず父母の協議で定め、その協議が整わない等の場合には裁判所が定めることになります。
その際の判断基準について、改正民法819条7項柱書は、
「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」 とされています。
また、共同親権とすることで子の利益を害すると認められる場合には、父母の一方を親権者と定めなければならないとし、子の利益を害する場合として次のものを挙げています。
・父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められる場合(819条7項1号)
・父母の一方が他から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権について協議が調わない理由その他の事情を考慮して、共同親権とすることが困難であると認められる場合(819条7項2号)