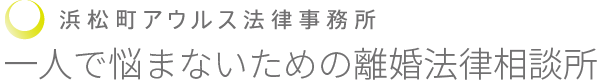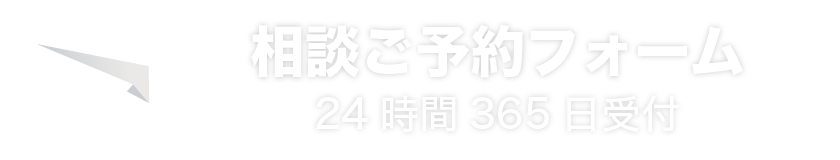共同親権にしたら、親権行使は常に他方の同意を得ないといけないのか
弁護士 長島功
今後導入予定の共同親権の制度により離婚後も共同親権とした場合、監護親は常に他方親権者の同意を得て親権を行使しなければいけないのでしょうか。離婚後、共同親権にしたからといって常に親権者双方の同意が必要になってくるのか、共同親権であったとしても単独で親権行使ができる場合はないのかについて解説していきます。
この点については、改正後民法の824条の2が親権を単独で行使できる場合を列挙していることから、順位みていきます。
1 一方のみが親権者のとき(同条1項1号)
離婚後に共同親権とはせず単独親権としたのであれば、もちろん親権者が単独で親権行使できます。 元々共同親権ではない場合なので、これは当然かと思います。
2 他の一方が親権を行うことができないとき(同条1項2号)
具体的には、親権停止など法的に親権行使ができない場合だけでなく、事実上親権行使ができない場合も含まれます。
具体的には、親権者の一方が行方不明・受刑中・重病等の場合です。
3 子の利益のため急迫の事情があるとき(同条1項3号)
共同で親権を行使する場合でも、父母の意見が対立して合意形成が困難な場合があろうかと思います。このような場合であっても、常に父母の協議や後述するように家庭裁判所の判断が必要ということになれば、子の利益を害するおそれが生じ得ます。そこで、子の利益のために急迫の事情があるときは、一方が単独で親権を行使できるとされています。
具体的には、受験願書の提出などの期限が迫っている場合、時間的に余裕のない緊急手術のための診療契約を締結する場合、DVや子への虐待から避難する必要がある場合等が挙げられます。
4 日常行為(同条2項)
日々の生活の中で生じる監護教育に関して、子に重大な影響を与えない日常的なものについても、父母の一方が単独で決定できます。
具体的には、食事や服装に関すること、習い事の選択、アルバイトの許可、通常のワクチン等です。
5 家庭裁判所が特定の事項について単独行使を認めた場合(同条3項)
共同親権者の間で意見が対立する場合、適時親権を行使できず、子に不利益が生じます。
そこで、父母間で協議が調わない場合で、子の利益のため必要があると認めるときは、父又は母の請求で家庭裁判所は特定の事項について単独で親権行使ができる旨定めることができるとされています。上記4つは家庭裁判所の判断がなくても単独行使は可能ですが、これは家庭裁判所の判断が必要な場合です。
急迫の事情があれば3で対応が可能ですし、日常的なものも4で対応ができますので、そうしたものに当たらない身上監護や財産管理行為、身分行為が対象です。
具体的には、居所の指定や重大な医療行為などで急迫の事情もない場合が挙げられます。