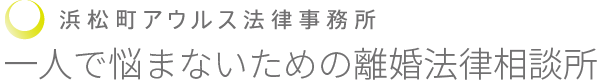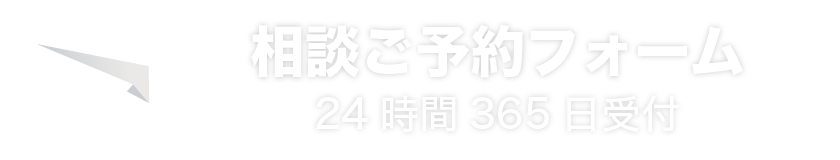共同親権と決めたら、もう単独親権にはできないのか?
弁護士 長島功
前回、今後導入予定の共同親権の制度について、まずは父母の協議により共同親権とするか、単独親権とするかを選択する制度であることをご説明しました。
ただ、夫婦間で真摯な話し合いがなされ、それに基づいて選択したのであれば良いのですが、暴力や威圧的な言動等により無理矢理合意をさせられる等の事態も想定されます。
そこで今回は、一度定められた親権者の変更について解説していきます。
1 改正民法における親権者の変更
改正民法では、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる」と定めました(改正民法819条6項)。
そのため、同条項に基づき、共同親権から単独親権に変更したり、父母いずれかの単独親権から他の一方の単独親権または共同親権に変更することは可能です。ただ、親権者の変更には「家庭裁判所」の判断が必要であり、当事者の協議だけで変更をすることはできません。
なお、現行法ではこの親権者の変更は「子の親族」が請求権者であるところ、改正民法では「子またはその親族」として子自身も変更を求めることが可能となっています。
2 変更を認める判断基準
上記のとおり「子の利益のため必要があるとき」に親権者は変更できるとされていますが、冒頭記載したとおり、特に協議で共同親権とする合意がなされ、その合意が真摯な合意によるものでなかった場合には対処の必要が出てきます。そこで改正民法は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、
・当該協議の経過
・その後の事情の変更
・その他の事情
を考慮する(改正民法819条8項前段)としています。
そして、上記のうち「当該協議の経過」を判断するにあたっては、
・父母の一方から他の一方への暴力等の有無
・家庭裁判所の調停の有無又は裁判外紛争解決手続の利用の有無
・協議の結果についての公正証書の作成の有無
といったものを勘案するとしています(改正民法819条8項後段)。
このように、一度親権者が決まったとしても、家庭裁判所の判断は必要ですが子の利益のため必要があれば変更をすることが可能です。特に協議で決められた親権者の場合、真摯な合意によらないケースも考えられるため、改正民法は具体的な考慮要素も挙げて一度決めた親権者を修正できるようにしています。